物件価格だけじゃない!?新築一戸建てと中古一戸建てにかかる住宅購入時のさまざまな費用
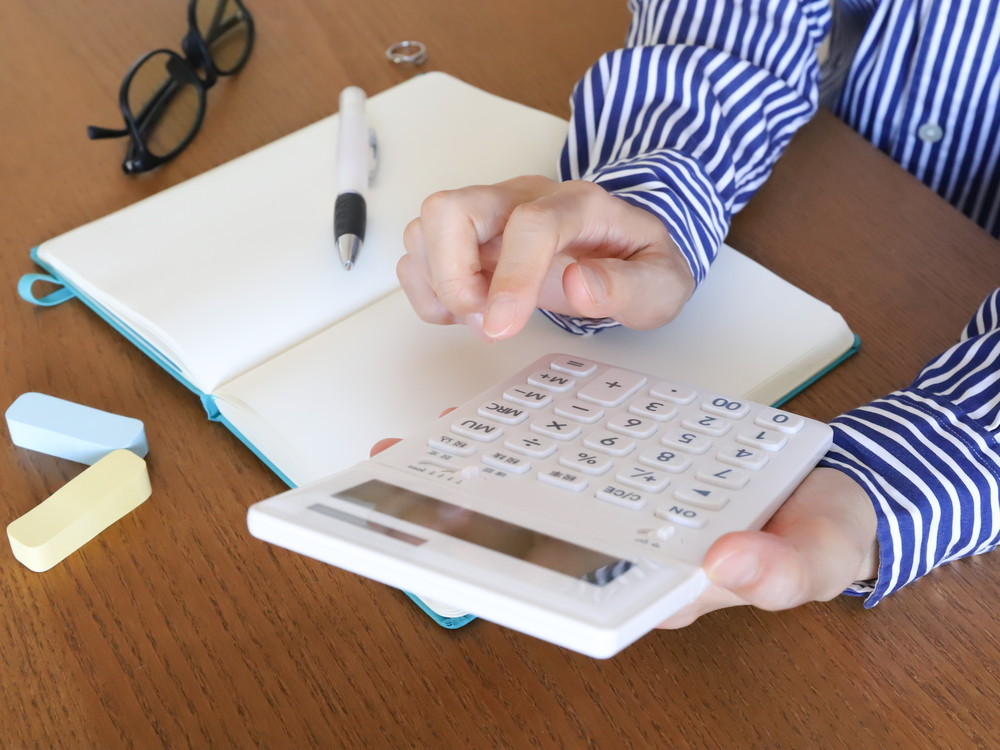
物件価格だけでない、住宅購入時のさまざまな費用
以下に、新築一戸建てと中古一戸建ての購入に関わる費用をまとめました。
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | |
|---|---|---|
| 物件価格 | 比較的高め | 比較的安め |
| 入居時のリフォーム | 必要なし | 必要なケースが多い |
| 消費税 | 課税対象 | 売主が個人なら対象外、事業者なら対象 |
| 固定資産税の軽減 | あり | なし |
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0 .15% | 固定資産評価額×0 .3% |
| 不動産取得税 | 固定資産評価額から1200万円が控除 | 築年数による |
中古購入時は入居前にリフォームをするのが定番
中古住宅と言っても状態はいろいろですが、比較的新しい家であっても、リフォームをしてから住みたいと考える人が多いです。
古い日本家屋を洋風化したい場合、本格的に変えようとするとコストが急に高くなり、結局は新築と変わらない価格になってしまうことも。
また、水回りは、リフォームをする代表的な場所。トイレをウォシュレット付きにしたり、浴室を丸ごと取り替えたりという方もいます。
ところで、中古の家の中には、「リフォーム済み」となっているものを見たことがあるのではないでしょうか。これは「買取再販」と言われるもので、個人が持っていた家を不動産会社が一度買い取り、リフォームをして再度売られるものです。
当然、リフォーム代は費用に含まれていますし、そこに事業者の販売管理費も含まれるので、決してお得な物件とは言い切れません。
その点、新築であればトイレやお風呂、ちょっとしたリフォームでは変えられないところに新しさがにじみ出てくるので、満足度が違います。
価格を比べるときには、単純に売られている価格だけで見るのではなく、リフォーム代と満足度も含めて比較することが大切ということです。

消費税は個人から購入する中古物件なら不要
物やサービスを購入するときに必要な消費税。新築物件は売主が不動産業者やハウスメーカーのため必要になります。一方、中古物件は売主が個人の場合、非課税です。
ちなみに、消費税が必要なのは建物に関わる費用のみ。売主が誰であろうと、土地代には消費税はかかりません。
固定資産税は新築なら、建物部分が3年間半額
固定資産税は、1月1日現在の所有者として登録されている人が市町村に対して納付するものです。ですので、家を購入した場合、翌年から対象となります。
税額は、
固定資産評価額×1.4%
で計算されます。
新築一戸建ての場合、3年にわたって建物部分にかかる固定資産税が半額(令和4年3月31日まで。床面積の制限あり)。一方、中古の一戸建てには軽減措置はありません。
(詳細については、各市町村のサイトなどを参照してください)

登録免許税は新築なら0.15%、中古なら0.3%
日本では、国内の土地や建物を建築したり、購入したりすると購入者を登記します。これにより、「この不動産は私が所有しているものです」と対外的に証明できるようになります。これを「所有権保存登記」や「移転登記」等と言いますが、この登録時に支払う税金が登録免許税です。
このうち、建物にかかる登録免許税に軽減税率が適用されています(令和4年3月31日まで)。
新築の場合(所有権保存登記) 建物分の固定資産評価額×0.15%
中古の場合(所有権移転登記) 建物分の固定資産評価額×0.3%
(登録免許税の軽減税率についてはさまざまな条件により税率が変わることがあります。詳しくは、国税庁のサイトを参照してください)
不動産取得税は新築なら1,200万円控除、中古は築年数による
不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことで、都道府県に支払います。このうち、建物について、一定の要件を満たせば、以下の軽減措置が受けられます。
新築の場合 建物分の固定資産評価額から1,200万円が控除
中古の場合 築年数によって控除額が減額(以下参照)
| 新築日 | 控除額 |
|---|---|
| 1997年4月1日以降 | 1200万円 |
| 1989年4月1日~1997年3月31日 | 1000万円 |
| 1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
| (以下省略) |
(詳細については、各都道府県のサイトなどを参照してください)
このように税金面では、個人から購入する中古一戸建ての消費税をのぞき、新築物件の方が優遇されていることが分かります。

最後に
ここまで、新築一戸建てと中古一戸建てにかかるさまざまな費用についてお伝えしてきました。
費用をしっかりと見積したうえで、新築と中古のどちらが良いか決めていきたいところです。
シアーズホームバースは、グループ全体で施工実績は10,000棟以上(2024年5月現在)になりました。注文住宅のクオリティを建売住宅で実現し、多くのお客さまの支持をいただいています。しかも売主でもあるので仲介手数料などはかかりませんし、ローンのサポートなども万全です。
新築一戸建てをお探しなら、まずはシアーズホームバースの物件をご覧になってください。



