持ち家と賃貸。住宅ローンと家賃を比較してみた

家を購入する金額で賃貸に住む場合、どれくらいの家賃を払えるのか?
結論から言えば、持ち家を買って一生住み続けるのと、賃貸住宅に一生住み続けるのを比較すると、住宅の質としてはほとんど変わりません。もちろん、比較方法によって違いは出るのですが・・・。
持ち家であれば住宅ローンの他に、固定資産税や修繕費などを加味しなければなりません。また賃貸住宅であれば、定期的に必要となる更新料や住み替えるたびに必要になる引っ越し代などがあります。こうなると、やり方次第の部分が大きく、一概にどっちがよいとは言いにくくなるわけです。
以下に、持ち家で支払う金額と、同等の金額で借りられる家賃を算出してみます。
まずは、一戸建てのシミュレーションから。
30歳の方が3,500万円の一戸建てを購入するとします。頭金はゼロ。90歳まで生きると仮定すると、購入する家には60年間住むことになります。
| 住宅ローン (3,500万円分) |
約4,500万円 (金利1.5%、35年固定、頭金・ボーナス払いなし) |
|---|---|
| リフォーム代 | 1,000万円(300万円×1回、700万円×1回) |
| 固定資産税 | 480万円(平均で年8万円と仮定) |
| 60年間の合計額 | 5,980万円 |
*計算を簡素化するため、住宅ローンの融資手数料や火災保険などは加味していません。
では、この5,980万円で賃貸住宅に住む場合、毎月どれくらいの家賃を出せるのでしょうか?
| 60年間の家賃予算 | 5,980万円 |
|---|---|
| 更新料 | 2年に1回(1ヶ月分)として計算 |
| 60年間の家賃平均月額 | 約79,700円(マンションの場合、共益費等も含む) |
*敷金や礼金は地域や物件による差が大きいので加味していません。
単純な計算ですが、3,500万円の家を買うのと、家賃8万円弱の家を比較すると、それほど変わりはないと感じます。いかがでしょうか?
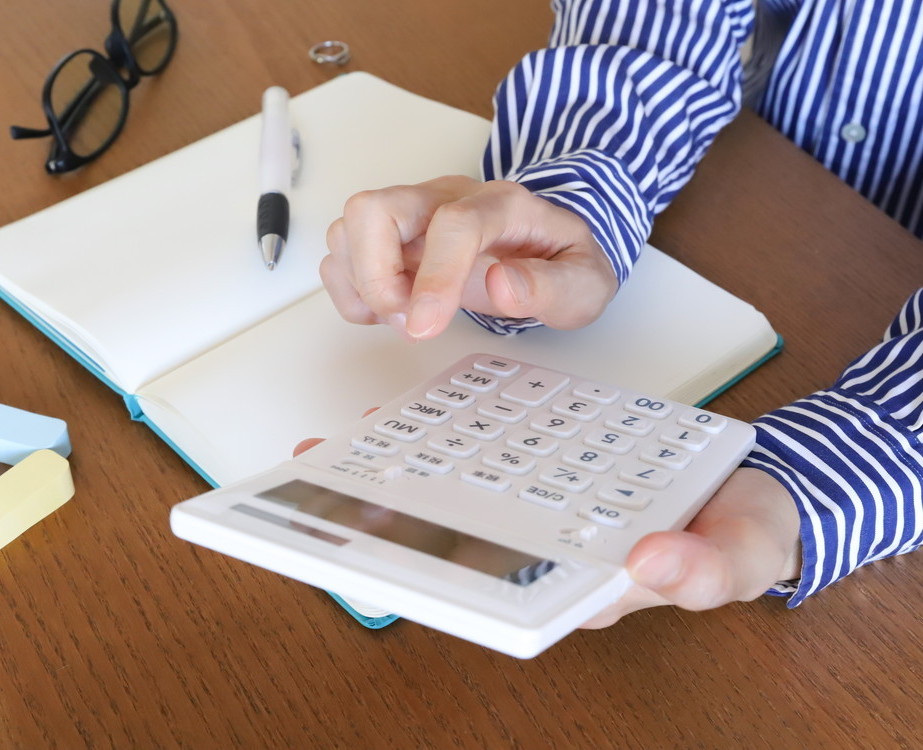
ただし、賃貸住宅にずっと住んでいると、亡くなった後は何も残りません。ですが、持ち家であれば、土地と建物が残ります。また、今は住宅ローン減税もあるので、これを加味すると持ち家の方がお得感は増すことになります。
持ち家か賃貸かは、どちらが自分に合っているかで選ぶべき
持ち家と賃貸住宅のどちらを選べばよいのかは、自分の価値観にあった方を選ぶべきです。もちろん、今だけを見るのではなく、将来も含めて判断するべきですね。
賃貸の方がむいている方
年齢が高くローン返済に不安がある人
住宅ローンは完済年齢を80歳未満としているところが多いようです。ですが、実際には定年後に払い続けるのは厳しいので、仕事をしている間に払え終えられるか、退職金で完済できる範囲で組む方が無難です。つまり、すでに年齢が高く、なおかつ退職金が期待できないのであれば、住宅ローンを組むべきではないでしょう。そのような場合は、賃貸住宅に住む方を選択する方が安定します。

安定した職についていない人
家を購入するときに借りる住宅ローンには審査があるので、これに通らない方は持ち家という選択は難しくなります。また、この先、長く働き続けるつもりがないという方も家を持つのは向きません。
持ち家の方がむいている方
退職までに住宅ローンの完済が可能な方
退職までに住宅ローンを完済できるか、または退職金で残った金額を完済できる方は、持ち家の方が合理的な選択だと言えます。現在の退職年齢は65歳。今後、70歳に伸びるかもしれませんが、人生100年時代であれば定年後、30年も生きるわけです。
この期間、ずっと家賃を払い続けることは不安なもの。住宅ローンを払い終わった後、安心して住める家があるのは大きな安心につながります。
子供に資産を残したい方
わが子に資産を残したいという方は、不動産で残すのが、一番無理がないと言われています。相続税が心配だという方がいますが、相続税の基礎控除額は意外と多いもの。その計算方法は以下です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(法廷相続人の人数×600万円)
都心で特に土地代が高いところや、広大な土地付きでない限り、多くは免税の範囲で収まります。

自分の一生の満足度を上げる家探し。ぜひ早めのスタートを!
家で過ごす時間は長く、癒やしの場所でもあるマイホーム。「いつか考えればいいや」と思っていて、後で持ち家を希望しても、ローンが組めない年齢では望まぬ結果になってしまいます。ぜひ、早めに考えをまとめることをおすすめします。
最後に
シアーズホームバースは、注文住宅のクオリティを建売住宅で実現し、多くのお客さまの支持をいただいています。しかも売主でもあるので仲介手数料などはかかりませんしローンのサポートなども万全です。
新築一戸建てをお探しなら、まずはシアーズホームバースの物件をご覧になってください。



